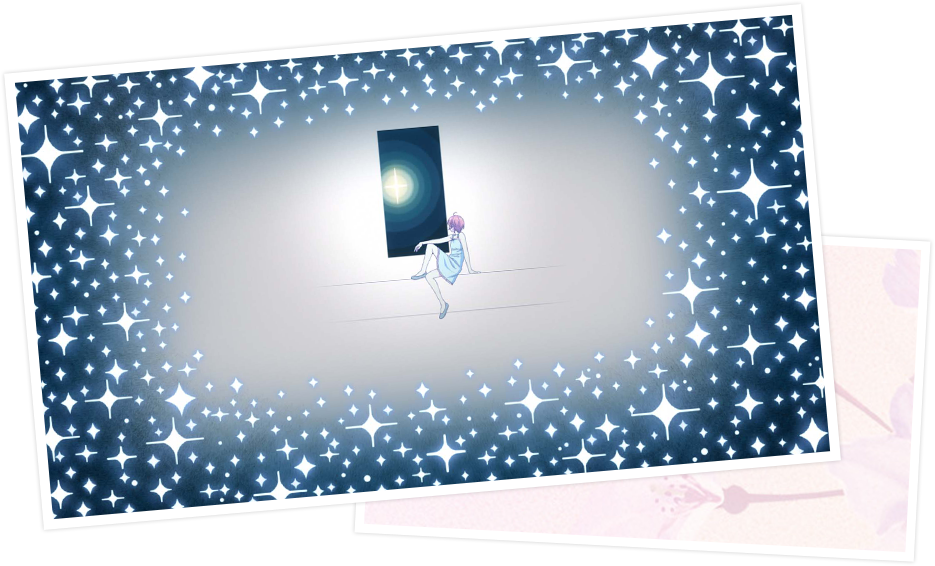教室には蜂蜜色の陽が射している。
とろりとした柔らかな光の中では、突如腕相撲大会が始まっていた。
他のクラスの生徒どころかなぜか上級生達まで乱入して、教室のあちこちで勝負が白熱している。
……なぜいきなり腕相撲。男の子っておもしろい。
私立桜咲学園高等学校は、全寮制の名門男子高。
ここでは自由な校風のもと、『個性豊かな』のひと言で済ませるには豊かすぎる男子達が高校生活を謳歌している。
あたし、芦屋瑞稀はその中で唯一人の女子だ。
もちろんみんなには内緒だけど。
「次は芦屋の番だよ」
「えっ? おれも参加するの?」
「当たり前だろ。優勝すれば1週間ジュース奢られ放題」
「うそ」
魅力的な景品に思わず腕まくりすると、横から手首を掴まれた。
「俺が代わりに出る」
「佐野……。へ、なんで?」
「なんでってお前……」
歯切れの悪い佐野との間を割って、虎みたいな勢いで中津が飛び込んでくる。
「ちょっと待った! 瑞稀の代わりやったらオレや」
「や、おれ自分で勝負するよ? ジュース権欲しいし」
「誰でもいいからさっさとしろ」
振り返ると、難波先輩が長い前髪をピンで留めて誰より本気の目をしている。
そうだった、この人達みんな、勝負事にはやたら熱くなるんだ。
輪になった生徒達が陽気に対戦を煽り、空手部長と演劇部長が恒例の小競り合いを始め、廊下から校医の梅田先生まで顔を出して、昼休みの教室は大騒ぎだ。
なんだか笑ってしまう。
あんまり賑やかで、あんまり幸せで。
きっとあたしは今、夢の中にいる。桜咲学園という名の夢の中に。
全てのはじまりは、3年前の夏休みだった。
日本のおばあちゃんちのテレビで偶然見た、中学生の陸上競技大会。
1人の選手の、青空にすっと弧を描いた綺麗なハイジャンプに、思いがけず目を奪われた。
そしてたぶん、心も一瞬で攫われてしまったのだ。
その鮮烈な印象はアメリカに帰国してからも色褪せることなく、むしろ日ごとに鮮やかさを増していった。
名前は佐野泉。
ハイジャンプの中学生選手。
あたしと同じ13歳。
知っているのは、たったそれだけだったのに。
とりあえず楽しいけれど、何かに夢中になることはない。そんなあたしの世界を、彼はくるりと変えてしまった。
「ねえ瑞稀、一体どんな魔法をかけられたの?」
親友のジュリアは笑う。
そう、きっとあれは魔法だったに違いない。
帰国後、あたしは太平洋の向こうの佐野泉について調べまくった。
まずはやっぱり検索から。だけど中学生陸上界のエースとはいえ、彼はいわゆる一般の男の子。SNSアカウントも見つからなくて、得られた情報はほぼなかった。
それでも、あきらめきれなくて。
やっと辿り着いた日本の陸上雑誌で、写真の入ったモノクロ記事を見つけた時の嬉しさは忘れられない。どんなに小さくても、これは彼に繋がるたったひとつの扉なのだ。
それからは月ごとの最新号に加えて、手に入るだけの雑誌のバックナンバーを海を越えて取り寄せた。費用捻出のため、パパの動物病院のお手伝いも頑張った。
少しでも彼に近づきたくて、いよいよ陸上まで始めてしまったあたしの見事な日焼けっぷりに、ジュリアはしみじみと息をついたものだ。
「まったく。瑞稀がこんな熱中型だなんて知らなかったわ」
そうだよね、あたしだって知らなかったよ。たぶん自分が1番驚いてる。佐野泉と(一方的にだけど)出会ってから見つけた、新しい自分がいっぱいいるんだ。
『1年の佐野泉が中学生男子新記録』
『2年生・佐野がまたも記録更新』
記事の中の、自らの記録を次々と塗り替えていく彼は、どこまでも眩しかった。
バイトでミスして落ち込んだ時も、友達とうまくいかない時も、スクラップ帳に増え続ける佐野泉の姿を見れば元気をもらえた。
誰かに強く憧れること。その憧れが力に変わること。
そんなのやっぱり、魔法だとしか思えない。
ハイスクールに進級したばかりのある夜、夢を見た。
あたしは、どこか知らない教室にいる。
大きく開いた窓から、柔らかい光と風が流れこんでくる。
あんまり心地よくてうとうとしていると、隣の席で誰かがくすっと笑った。
目を開けるとそこには佐野泉がいて、面白そうにこちらを見つめている。
ん? なに?
尋ねると、彼は無言で自分の口元を指した。
1文字ずつ区切るように動く唇を、真剣に目で追っていく。
えっと……『よ』『だ』……『れ』?
ちょ、あたし、よだれ出てた!?
慌てて口元を拭うと、佐野泉は顔をくしゃくしゃにして笑った。
近づいてみたい衝動で思わず手をのばした瞬間、彼の姿は消えてしまう。
「待って」
自分の声で目が覚めた。
残されたあたしの掌だけが、むなしく宙に浮かんでいる。
「ちょっと瑞稀、ジュース零れてるわよ!」
「えっ? わあっ!」
ママの声で我に返ると、注いでいたはずのオレンジジュースがグラスから溢れ出していた。投げてもらったタオルをキャッチして、慌ててテーブルを拭く。
「なあに朝からぼーっとして。考えごと?」
「う、うん。そんなとこかな」
大好きなオムレツも今朝はなんだか味がしない。まだ半分夢の中にいるみたいだ。
佐野泉ってあんな風に笑うのかな。
隣で見る風景は、どんな色をしてるんだろう?
どうしてあんなジャンプを跳べるのか、聞いてみたかった。
夢だけじゃ全然足りないよ。
――彼と友達になりたい。
そんな思いは、この時から風船みたいにどんどん膨らんでいった。
そして数か月後、事件は起きた。
「どうしようジュリア!」
飛び込むようにベッドに乗る。
あたしの部屋ではベッドはソファと兼用。ジュリアも慣れたものですっかり寛いでいる。
「今月号にも佐野泉の記事が載ってないよ~!」
目ぼしい大会がなかったのかもしれないし、調子が悪かったのかもしれない。佐野泉だって人間なんだし、当然だよ。
だけど、先月も情報ゼロだったのに!
ショックな気持ちを共有したかったけれど、ジュリアはうちのママお手製のレモネードを呑気にちゅるちゅると吸っている。
「事件なんて言うから何事かと思ったら」
グロスに淡く光る唇が、ようやくストローから離れた。
「世界大会なんかの選手でもない、ただの学生よね? 雑誌に毎月載ってないのなんて当たり前じゃない?」
「うっ。そりゃあ……まあ」
スマホに視線を移そうとするジュリアに、諦め悪く食い下がる。
「でも、これまではどんなにちょっとでも必ず何か情報があったの。なんか、彼を熱心に追っかけてる記者さんがいるっぽいんだよね」
そもそも中学生選手の記事は少ない。でも! だからこそ、ひとつひとつがあたしにとっては大事な扉なのだ。
なのにこのままじゃ、彼への扉が閉じちゃうのでは!?
「ねえ。あなたのスターに夢中なのもいいけど、あたし達自身のことを考えましょ」
「あたし達のことって?」
「ハイスクール生活はティーンの花! これから楽しいイベントが山盛りなんだから。まずは来月のダンスパーティー、気合い入れてくわよ」
すらりと長い腕がのびてきて、肩を抱き寄せられる。
あたし達がハイスクール生になったのは、去年のこと。どうやら日本とは学年のシステムがずれているらしい。それだって、佐野泉に興味を抱かなければ知らなかった。
来月には、佐野泉も高校生になるはず。日本の高校かぁ……。
「……んん?」
頭の中で、ファンファーレが鳴った気がした。
――なんで今まで思いつかなかったんだろう。
こぼれた呟きに、ジュリアがぱっと反応する。
「さっそくダンスのパートナー候補でも思い浮かんだ?」
「あたし、佐野泉の学校に転校しちゃおうかな」
そうだよ、簡単なこと。
扉が閉じたって、自分で開ければいいんだよね!
「はいはい、がんばってちょうだい」
冗談だと思っているらしい彼女は、スマホに目を落としてドレスを検索し始める。
こっちは全力で本気なんだけど。
考えたら、全然不可能なんかじゃない。
別の国っていったって、日本もアメリカも同じ地球の上にあるんだもん。
言葉だって問題ないし。これってもう、行くしかないってことでは?
パパ、ママ、あたしを日本語で育ててくれてありがとう!
見晴らしの良い坂道を自転車で一気に下る時みたいに、心地よい高揚感が全身を駆け巡る。この胸の高鳴りが指す矢印の方へ、一直線に進むのだ。
その日から着々と、転入に向けてのリサーチを始めた。
夜な夜な部屋にこもっては媒体の隅々まで目を光らせ、スマホとにらめっこする。
そうしてようやく掴んだ佐野泉の進学先は、『私立桜咲学園高等学校』。
文武に秀でた生徒達が集まる、一芸入学や特待生制度もある名門男子高らしい。
学校名がわかってしまえば、こっちのもの――……あれ?
「名門『男子高』っ!?」
思わずスマホを取り落とす。
慌ててしゃがみ込むと、机の角に思いきり頭をぶつけた。
鈍い音と共に、机の上に積み上がっていた雑誌やノートが崩れ落ちる。派手に床に散らばったそれらの中には、大切なスクラップ帳もあった。
「あーあ……」
ため息が涙に変わりそうになるのを、ぐっと堪える。
拾おうとして、開いてしまっているスクラップ帳のページが目に入った。貼られていたのは、何度も読み返した、佐野泉の短いインタビュー記事。
『努力はきっと報われる。後は自分の力を信じるだけ』
いつもあたしを励まし続けてくれたお守りみたいな彼の言葉だ。なのに、今は色を失くしてしまったよう。
努力の入口さえ壁に塞がれた時は、一体どうしたらいい?
佐野泉、なんで男子高を選んだの。
これまではたしか共学だったよね!?
やっぱり諦めるしかないの?
でも~~!
メリーゴーランドみたいに、ぐるぐると考えが廻り続ける。
机に伏したまま動かないあたしを、ジュリアが軽くつついてくる。
「最近妙に元気だったのに、一体どうしたのよ。ランチタイム終わっちゃうわよ?」
「……あたしはいい。ジュリアひとりで食べてきて」
「信じられない、瑞稀が食事抜きなんて! 緊急事態だわ」
とにかく何かお腹に入れなさい、と強引にカフェテリアに引き摺っていかれる。
ジュリアはプリンとサンドイッチを注文して、「シェアするわよ」とあたしの前に置いた。
「大きな壁にぶちあたってゲームオーバーなの。しばらくそっとしといて」
「らしくないわね。壁なんかあったって、壊して突き進むのが瑞稀でしょ?」
「……あたしって、そういうイメージ?」
「少なくとも、スターが現れてからはね」
「え……?」
「あの時だってそうだった。あなたは正面からぶつかってきてくれたわ」
綺麗なウインクが飛んでくる。
「忘れたわけじゃないでしょ?」
……うん、もちろん覚えてる。
以前、あたしとジュリアは、ちょっとしたすれ違いが原因でぎくしゃくしていた。
どうにかしなきゃと思うほど、距離は開いていくばかりで。このままじゃダメだってわかってるのに、どうしても話しかける勇気が出なくて。
半ば諦めかけてしまっていた頃に――日本で、彼のハイジャンプを見た。
それからも次々と自己新記録を更新していく彼の頑張りに背中を押されて、正直な気持ちでもう一度ジュリアに向き合うことができたんだ。
「そのおかげで、今のあたし達がいるのよ」
膝に置いたままの手に、ジュリアの手が重ねられる。
そうだった。佐野泉を知る前のあたしには、とてもできなかった。彼がくれた力で、この大切な親友との縁を結び直せたんだ。
「大丈夫。瑞稀らしく壁を乗り越える方法が、きっと見つかるわ」
プリンをのせたスプーンを、ジュリアが唇の前に差し出してくれる。
口に入れると、優しい甘さがじんわりと広がった。
あたしらしく。
どんなことでも無理だなんて決めつけずに、前へ踏み出そうか。
「ありがとジュリア。やっぱり最高の親友だよ!」
気持ちのまま思いきりハグすると、頬にキスが降ってくる。
『努力はきっと報われる。後は自分の力を信じるだけ』
くよくよ考えるより、その言葉を抱きしめて、跳んでみよう。
町じゅうがカリフォルニア・ポピーの花に彩られる季節。
ジュリアはいつものように、あたしのベッドの上にいた。
「せっかく綺麗なストレートロングなのに、本当に切っちゃうの?」
「うん。バッサリお願い。男の子みたいなショートヘアにしたいんだ」
かなり手こずったパパ達の説得も諸々の手続きもやっとクリアして、いよいよこれが桜咲学園転入への最後の準備だ。
その場にはやっぱり、ジュリアにいて欲しかった。
「ということで、はい」
カット用のハサミを差し出すと、青い大きな瞳がさらに丸くなる。
「ちょっと、まさかあたしに切らせるつもり!?」
「大丈夫だよ、ジュリアならできるって。あたしよりずっと器用だもん」
「だめよ、無理に決まってるじゃない。しかもショートヘアだなんて!」
「お願い~! アイスおごるから」
結局、どんな条件にもジュリアは首を縦には振らなかった。
まあ何とかなるか。男の子に見えさえすればいいんだもんね。
あたしが見つけた方法。それは男子として桜咲学園に転入すること。
もちろん家族にも内緒だ。無茶だってわかってるけど、自分を信じて進むのみ。
ひと筋掴んだ髪にハサミをあてて、鏡を見つめる。
よし、いくよ。
「鏡よ鏡~……」
今度は自分で魔法をかける。彼の、佐野泉の世界に飛び込むために。
そろそろ、昼休み終わりのチャイムが鳴る時間だっていうのに。
腕相撲大会はどういうわけか相撲大会に変わって、ますます盛り上がっている。
今、目の前にあるこの光景。この人たち。
佐野。中津。野江。関目。萱島。中央。難波先輩。梅田先生。姫島先輩。天王寺先輩。ほかにも、みんなみんな。
毎日誰かが揉めたり力を合わせたり泣いたり怒ったり、思いきり笑い合ったり。
全てがおれのあたしの夢見たもの。
「芦屋、なにニヤついてんだ?」
「べ、別にニヤついてなんかないよ。それより佐野、おれと相撲で勝負する?」
「は!? お前マジでやめとけ」
「いてっ」
「いいな、他の奴とも絶対やるなよ?」
手加減されたデコピンの優しい痛みも、少し低めの佐野の声も。
あの日々の決意の先で、夢のような現実になった。