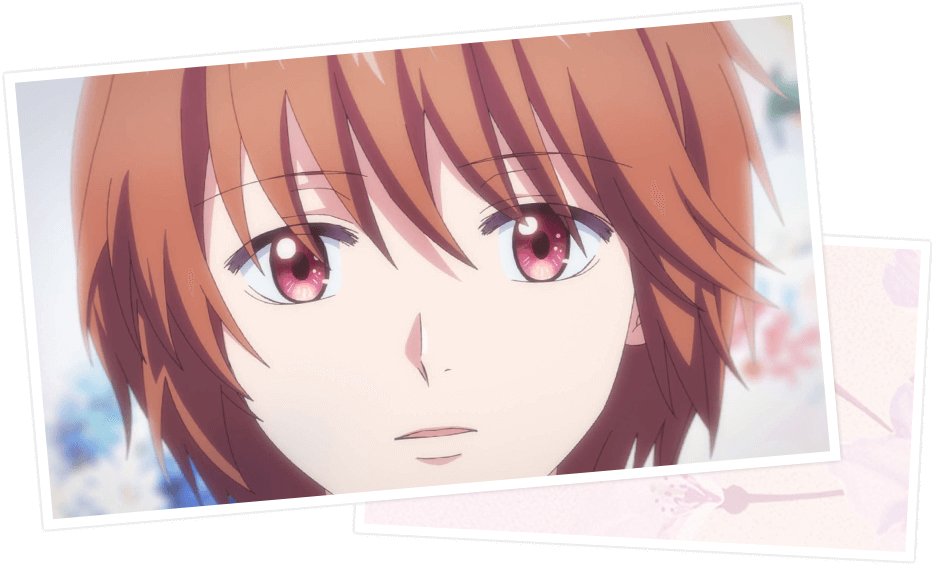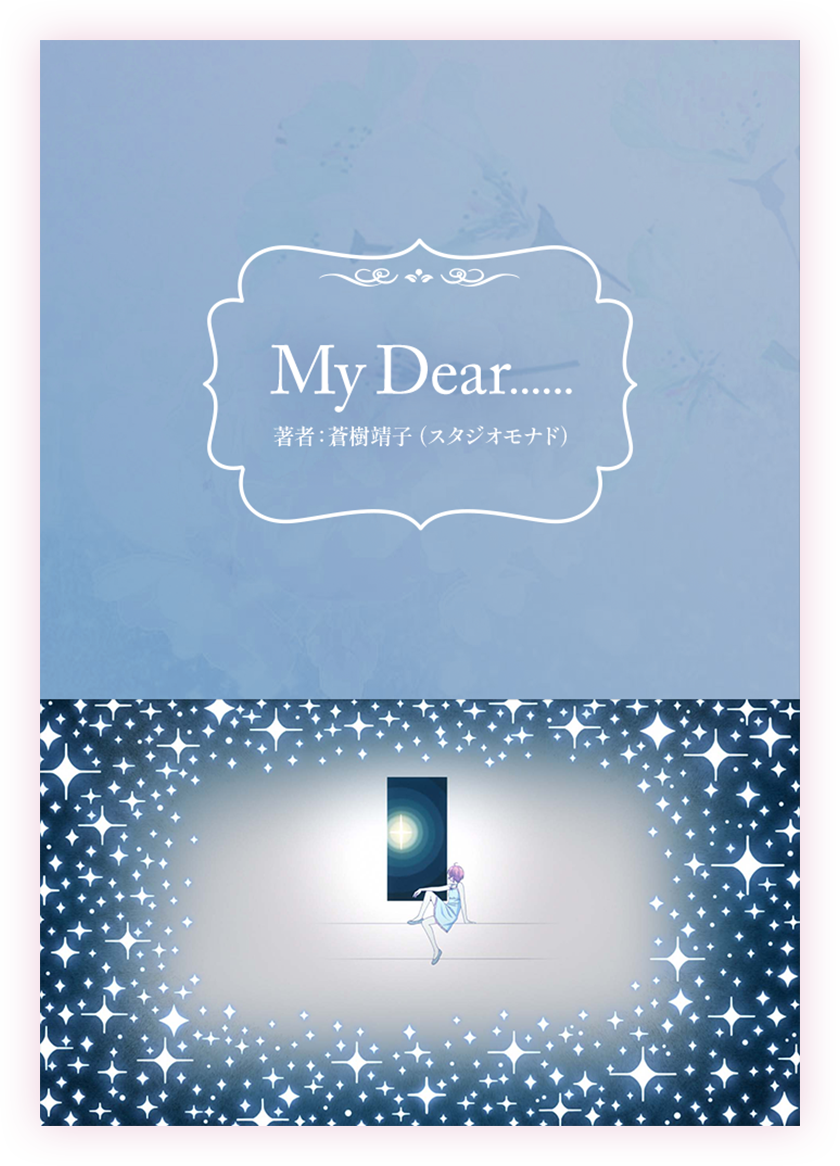
私立桜咲学園の第2寮棟。
昼間は生徒たちのうるさいくらい賑やかな声で溢れているけど、この時間は流石にしんと静まり返っている。
あたしは205号室に戻ると、なるべく静かに椅子に腰かけた。
そしてお気に入りのマグカップで食堂で作ってきたミルクティーを一口飲む。
「ふう……」
ほっと心地よい熱が巡り、心と体を解いてくれる。
だが今日の出来事と、この胸を揺らす熱はミルクティーでは決して流せないものだった。
ちらりと後ろの2段ベッドを見ると、すでに下の段のカーテンは引かれている。
きっと今頃佐野は夢の中だろう。
部活も忙しいのに、あんなことまでしてくれたんだもんな……。
机の上には『My Dear』と書かれたピンク色の封筒と、桜で出来た栞、そして四つ葉のクローバーが2枚置いてある。
あたしは四つ葉のクローバーにそっと触れると、呟いた。
「佐野……」
初めは誰よりも綺麗に跳ぶ姿に憧れた。
そして今は、どんな高い困難でも逃げずに立ち向かう勇気に惹かれている。
あたしはミルクティーをもう一口飲むと、ゆったりと椅子に体を預け、目を閉じてここ数日の出来事を思い出すことにした……。
× × ×
きっかけは1週間前、ジュリアから送られてきた小包だった。
「あれ? 何もメッセージ来てなかったけど、なんだろう?」
開けてみると、そこにはクッキーやチョコレート、それにアメリカであたしが好きだったソースなどが、ぎゅうぎゅうに詰められていた。
思わぬ支援物資にあたしは歓声をあげた。
日本食は美味しいし大好きだけど、時々このカラフルでおもちゃのような見た目と、パンチのある甘さが無性に恋しくなるときがあるのだ。
「持つべきものは親友だよね……ん?」
段ボールの底には『My Dear』と書かれたピンク色の封筒があった。
中を確認してみると、ジュリアからの手紙と、桜の押し花で作られた栞が入っていた。
『Hi瑞稀! あなたと一緒に見たバルボアパークの桜よ。いつでも思い出せるように栞にしてみたの』
バルボアパークはあたしが住んでいたバークレーと同じくカルフォルニア州にある。
同じ州と行っても、結構遠くて正直日帰りは厳しいんだけど。
公園内には日本庭園があり、毎年『桜祭り』を開催していて、あたしが日本に行く前、ジュリアが『桜祭り』を見に行こうと誘ってくれたのだ。
真っ青な空の下、白く輝き舞う花弁を見ながらジュリアは言った。
『瑞稀、日本とアメリカはこの空で繋がっているわ。忘れないでね』
日本に来てから1年くらいしか経っていないのに、なんだか遠い記憶に思える。
ジュリアの手紙を読み終えると、あたしはスマホを手に取った。
佐野は難波先輩に用事を頼まれていて、今部屋にはあたしだけだ。
アメリカはまだ寝る時間じゃないし、ビデオ通話をしても迷惑じゃないだろう。
数回のコール音の後、明るい声がした。
「Hi瑞稀!」
「Hiジュリア! プレゼント、届いたよ! ありがとう!」
「ふふふ。たまにはサプライズもいいでしょう?」
「うん! お菓子もだけど、桜の栞、本当に嬉しかった! 大事にするね」
「貴女の笑顔が見られて何よりだわ……それはそうと……彼とはどうなの?」
「え?」
「え? じゃないわよ。憧れのハイジャンパー、佐野よ。日本では『サクラサク』? というのだったかしら? そろそろ恋人になっても良いころよね?」
「こ、恋人!? そ、そんなのまだ早いって!」
「ちっとも早くないわよ、まったく。もう1年くらい経ってるじゃない。せめて何か進展は?」
ジュリアの言葉に、佐野からキスされた時を思い出して、耳が熱くなってきた。
でもあれは不測の事態だ。
佐野は酔っていてその時の記憶は残っていなかったし、あたしもショックの方が大きかった。
決して嫌ではなかったけれど、どちらかいえば切なく、ほろ苦さが滲む思い出だ。
それでも佐野とキスをしたという事実は、あたしの心の奥底に檸檬色の跡を残していたのだった。
あたしは速くなる鼓動を押し隠して答えた。
「……佐野は、あたしの憧れで、自慢の友達だよ」
あたしの言葉を聞いたジュリアは深いため息をついた。
「はぁ……あのねえ、瑞稀? 貴女はとても魅力的な女性よ。しかも想い人を追いかけてたった1人で国を渡る勇気と行動力もある。そんな瑞稀に好意を寄せられて、なびかない男性はいないわ!」
「それって親友の欲目じゃない……?」
「事実を言っているだけよ」
あたしは言い切るジュリアに戸惑った。
何故なら……。
「……そもそも佐野はあたしのこと、男の子だと思ってるんだよ?」
そう、あたしが今、心地良く佐野の傍にいられるのは、男の子の姿をしているから。
『佐野泉の友達』だからだ。
男の子として桜咲学園に転入するという選択した結果を、あたしは少しも後悔はしていない。
でも次の言葉を続けようとすると、胸が緩やかに締め付けられる。
「……佐野と恋人なんて、ありえないよ」
自分の言葉で傷つくなんてどうかしていると思うし、ジュリアを心配させたくはない。
だからなるべく普段通りのテンションで言ったつもりだけど、ジュリアはきっとあたしの言葉に隠されていた痛みに気が付いたのだろう。
しばらく黙った後、こう尋ねてきた。
「……ねえ、瑞稀? あなたにとって、佐野泉はどんな存在?」
「どんな存在って……だから、自慢の友達で、大事な人だよ」
「大事な人、ねえ……もっと具体的な言葉を聞きたいわ」
「具体的……」
「アメリカで佐野に憧れていたときと、今の貴女。何が変わったの?」
「それは……」
ジュリアの声は真剣だ。
あたしもちゃんと考えないといけない。
まず最初に思いついたのは、長いまつげに縁取られた佐野の瞳だった。
「……佐野の瞳って、とても綺麗なんだよ。カルフォルニアの空みたいに澄んでいて、でも時々寂しそうな色をしてる時もあって………目が離せない」
最初はうまく話せるか分からず不安だったが、1つ紡ぐと、どんどんと言葉が溢れ出してくる。
「それから、佐野があたしの名前を呼ぶときの、低くてちょっとぶっきらぼうだけど優しい声。不思議なんだけど、どんなに人が多くても気が付くの」
あたしは自然と笑みが零れてきていることに気がついた。
「あとは『仕方がないな』って言いながら、あたしの頭をぐしゃぐしゃって撫でる手の大きさも、温かさも……佐野と実際に出会わなければ知らなかった」
思えばアメリカにいた時の佐野への想いは、きっと朝空に浮かぶ星のようなものだった。
決して目に見えなくて、例え触れられなくても、『そこにある』と信じるだけでキラキラとした気持ちになれる。
そんな星だった。
今は手を伸ばせば佐野の肌に触れられる。
胸の鼓動を感じられる。
そんな距離にやってきた。
でもその距離が時折、アメリカよりも遠く感じるときもある。
ちょっとした勘違いやすれ違いもあって、涙で心がぐちゃぐちゃになるときもある。
美しい星を想うだけだったら、きっとこんな痛みは感じなかっただろう。
でも、今はそんな傷すら愛おしい。
佐野と出会って、言葉を交わして、一歩ずつ思い出を築けていけるのが嬉しいんだ。
だから……。
「……アメリカにいた頃と、今。あたしは変わってないけど、変わったんだよ」
あたしはビデオ通話越しにジュリアに自信を持って微笑んだ。
「佐野は恋人じゃない。でも大事な人なの」
あたしの言葉にジュリアはちょっと呆れた、でもあたしの大好きな笑顔になった。
「……そう。なら健闘を祈るわ」
「ありがとう」
「忘れないで、あたしはどんな時も貴女の幸せを祈っているわ。My Dear」
「あたしもだよ」
そう言って、あたしたちはビデオ通話を切った。
桜の栞を手に取り、眺める。
アメリカでは桜の花言葉は確か『精神の美』。
まさにジュリアにぴったりだ。
「あたしは幸せ者だなぁ……」
遠く離れていても見守ってくれる親友に、傍にいるだけで陽だまりの夢を見せてくれる好きな人。
温かい想いに包まれて、あたしは眠りについた。
× × ×
次の日の放課後、あたしは学園の中庭に這いつくばっていた。
四つ葉のクローバーを探すためだ。
ジュリアがくれたバルボアパークの桜の栞、それのお返しに何か特別なプレゼントを贈りたかったのだ。
(それで四つ葉のクローバーだっていうのは、ちょっと安直かもしれないけど……)
思いついてしまったのだから、仕方がない。
あとは行動するだけだった。
「……うーん、なかなか見つからないなぁ……」
土に汚れた手で汗を拭っていると、背後から良く知った声がした。
「芦屋、何してんだ?」
「穴掘りかいな?」
「裕次郎じゃないんだから……」
振り返って見ると佐野、中津、関目、野江、萱島といういつものメンバーがいた。
「みんな! これから部活?」
「ああ」
「それはそうと、何してん?」
「実は……」
あたしはジュリアとの会話の内容は伏せて、『アメリカの親友に四つ葉のクローバーを贈りたい』とだけみんなに説明した。
すると中津が大きな目を輝かせ、自分の胸を叩きながら言った。
「よっしゃ! そういうことなら、オレらも手伝うで!」
「えっ!? で、でも、みんな部活が……」
佐野は遂にまた跳ぶことができたけど、まだ自分と向き合う時間が必要だと思う。
中津だってサッカーの試合を控えているはずだ。
関目も野江もおそらく同じような状況だろう。
「みんなの大事な時間を無駄にしちゃうのは申し訳ないよ……」
すると佐野が苦笑しながら、あたしの頭をポンと撫でた。
「馬鹿だな」
言葉とは裏腹に佐野の声と手は優しくて、みんなの前なのに、軽く胸がときめいてしまう。
「友達のために使う時間は無駄じゃないだろ」
佐野の言葉に中津たちも頷く。
「瑞稀のダチやったら、オレらにとってもダチ みたいんなもんちゅーこっちゃ!」
「みんな……ありがとう!」
「よっしゃ! それじゃ四つ葉のクローバー探しや!
狩って、狩って、狩りつくすでー!」
「普通に迷惑だな」
「四つ葉のクローバー探しって、小学生以来だな」
「萱島、オーラで見つけらんねーの?」
「無理。植物のオーラって、みんな似てるから」
わいわいとおしゃべりしながら一緒に泥まみれになって四つ葉のクローバーを探してくれる仲間たちに囲まれて、あたしは改めて彼らへの感謝と、こんな素敵な仲間に恵まれた幸運に感謝した。
(ジュリア……やっぱりあたし、日本に来てよかったよ)
――だけど結局、みんなが一生懸命探してくれても、四つ葉のクローバーは見つからなかった……。
× × ×
その日の夜、あたしは自分の部屋で机に突っ伏しながら、ため息をついていた。
「……四つ葉のクローバー、見つからなかったなぁ……」
頑張っても見つからなかったものは仕方がない。
だけど『せっかく佐野たちが一緒に探してくれたのに』と申し訳ない気持ちになった。
「はぁ……」
2度目のため息をついた時、ドアが開いて佐野が部活から帰ってきた。
「佐野! お帰り。今日も頑張ってたんだね。お疲れ様」
「ん」
佐野はあたしをじっと見つめてくる。
「芦屋、お前、飯は?」
「あ……」
佐野に聞かれて、あたしは初めて夕ご飯を忘れていたことに気が付いた。
「あ、あはは! なんかぼうっとしてたら、忘れちゃったみたい」
「……そうか。なら、ほら」
そう言うと、佐野はあたしに何かを投げてきた。
「わっ!?」
受け取るとそれはあたしが好きな桃ジュースだった。
「やる。水と間違えて買っちまったんだ。それ飲めば、少しは腹が膨れるだろ」
「間違えたって……」
学園の自販機には確かに水と桃ジュース、両方売っている。
でも大分離れた位置に並んでいて、とても間違えるようには思えない。
(佐野、あたしが落ち込んでるだろうって、わざわざ……)
佐野のこういうぶっきらぼうな小さい優しさは宝石のように輝いて、あたしの心の種をまた1つ芽吹かせるのだった。
「……ありがとう。じゃあ遠慮なくもらうね」
「おう」
佐野は桃ジュースを飲むあたしの横に座ると聞いてきた。
「四つ葉のクローバーを渡したかった相手って……」
「ジュリアだよ。アメリカにいる親友」
「いつも電話とか、手紙のやり取りしてんだろう? なんでわざわざ?」
「ジュリアが栞を作って贈ってきてくれたんだ。思い出の場所の桜を押し花にしてくれて……ジュリアはおれの『My Dear』だ」
あたしはジュリアの顔を思い出して笑った。
「『おれは日本に来て幸せだよ』『君の幸せを祈ってるよ』……って、ジュリアには伝えたい。親友だからこそ、ちゃんと形にするのが大事ってこともあると思うんだ」
「……なるほどな」
佐野が何か考えているような顔をして頷いた。
と、その時、あたしのお腹がびっくりするぐらい大きな音を立てた。
驚きと恥ずかしさで顔が真っ赤になる。
「あっ! こ、これは! その!」
佐野は明らかに笑いをこらえていた。
「自販機でなんか買ってくるか。俺も腹減ったし」
「……うん!」
あたしは笑って佐野の隣を歩きだした。
× × ×
佐野の様子がおかしくなったのは、次の日からだった。
部屋に帰ってくるのがとても遅く、しかもなんだかそそくさとベッドに入ってしまう。
最初は部活の練習が長引いて疲れているのかと思ったのだが……。
「泉? 部活、普通に終わっとるみたいやけど?」
「え? じゃあ、自主練とか?」
「自主練……やないと思う。関目が外走っとるときに、近くの公園や、川っぺりにおるの見た言うてたけど……裕次郎の散歩ちゃうか?」
裕次郎の散歩はここ数日はあたしの担当だった。
では何故佐野は戻ってくるのが遅いんだろう?
(あたしと顔を合わせたくない理由があるとか? でも、朝起きた時とか授業の時は普通だったし……)
佐野が何の理由もなくあたしを嫌いになることなんて絶対にない。
そんな確信と信頼はこの約1年間で出来ていた。
だけど恋心というのは本当に素晴らしくて、どうしようもなく厄介だ。
心に刺さった『不安』という名の小さな棘は、時に世界の終わりくらい人を怯えさせ、振り回すことがあると、あたしはこの1年で身をもって学んでいた。
(今回はそんな大げさなことじゃないと思うけど……)
『佐野に避けられているかも?』という考えは黒い染みとなって拡がり、あたしの胸を重くするのだった……。
× × ×
その日の夜……つまり、今日の夜だ。
あたしは決戦の準備をして佐野を待っていた。
(分からないなら、直接聞いてみるしかない!)
悩んでいるのは性に合わないのだ。
(佐野が何を考えているのかは分からない。でももし、あたしが何かしちゃったのなら、ちゃんと謝ろう)
そう決めて、あたしは今か今かと佐野の帰りを待っていた。
佐野は今日も帰りが遅く、夜も更けてから部屋に戻ってきた。
「ただいま……」
「お帰り……」
佐野に『話がある』と言い出そうとした瞬間、彼はあたしに手を出してきた。
「これ」
見るとその手にはなんと四つ葉のクローバーが握られていた。
「えっ……?」
突然の展開に、あたしは思わず息を呑んでしまった。
「たまたま見つけたんだ。アメリカの友達に贈ってやれよ」
「あっ……ありがとう……」
あたしはまだ驚きが勝っていた。
何故佐野が四つ葉のクローバーを? 一体どこで?
混乱するあたしに佐野はさらに続けた。
「あと、こっちはお前に」
その手の上には、もう1枚の四つ葉のクローバーがあった。
「……おれに?」
「お前も、前にお守りくれただろ」
確かに陸上競技会の地区予選の時、佐野を少しでも応援できないかと思って、お守りは渡したけど……。
「で、でもあれって、縁結び用だったし!別に佐野はあれがなくてもきっと跳べたと思うし……!」
「関係ない。俺が贈りたかっただけだ。『ちゃんと形にするのが大事なこともある』……だろ?」
「佐野……」
「俺でも四つ葉のクローバーが『幸運』の象徴だってことぐらいは知ってる……良いことあるといいな、お前も、お前の友達も」
あたしは佐野に抱き着きたくなる気持ちを必死で抑えて言った。
「もう、滅茶苦茶良いことあったよ! ありがとう佐野!」
あたしの言葉を聞くと、佐野は澄んだ瞳を三日月のように細めて笑った。
× × ×
――あたしはゆっくりと目を開けた。
既にミルクティーは大分ぬるくなってしまっている。
ふと、もう一度2段ベッドの下の段を振り返って見る。
(佐野……)
最初はびっくりしていて気が付かなかったけど、きっと佐野はここ数日、部活の後、ずっと四つ葉のクローバーを探してくれていたのだろう。
あたしと、あたしの大事な親友のために。
何の見返りもなく、ただあたしが喜ぶだろうという気持ちだけで。
(もう、どれだけ好きにさせれば気が済むんだよ……)
もうこれ以上好きになることはない。
……そう思っているはずなのに……。
『練習姿、かっこよかったな』
『うどんを食べるところがなんだかセクシーだな』
『うっかり食べてしまった甘いお菓子に険しくなる眉も可愛いな』
……なんて佐野の新しい輝きに気が付いて、あっさりとあたしの好きは更新されていく。
ちょっと自分でも怖いくらいだ。
机の上の四つ葉のクローバーを見つめてみる。
佐野は優しい人だから、きっと中津でも、関目でも、場合によっては梅田先生であっても、親しい人が困っていて、真剣に悩んでいたら、きっと手を差し伸べるだろう。
でもこの四つ葉のクローバーは、あたしだから、芦屋瑞稀のためだからここまで必死になって探してくれた。
……そう自惚れてしまいたくなってしまう。
佐野は四つ葉のクローバーは『幸運の象徴だ』と言っていた。
それは間違ってはいない。
でも他にもこんな花言葉もあるのだ。
『Be Mine――私のものになってください――』。
だから佐野に四つ葉のクローバーを手渡された時、温かな指先が触れた時、痛くなるほど心臓が高鳴った。
もちろん、佐野にそんなつもりがないのは分かっている。
だけどあたしは甘い夢を見ずにはいられなくて、夜露に輝く小さな緑色のハートを見て、涙が出そうになったんだ。
あたしは零れ落ちそうな想いを込めて、四つ葉のクローバーにそっと唇を寄せる。
「ありがとう……My Dear」
『My Dear』というのは特に親しい人に使う言葉だ。
例えば親友や家族、そして恋人に。
今も佐野はあたしにとっては『My Dear』だ。
十分過ぎるほど、優しさをもらっている。
だけどあたしは、いつか凛とした唇から零れる吐息を感じながら彼の隣を歩きたい。
特別な熱を込めて名前を呼んで欲しい。
友達じゃない『おはよう』を言ってみたい。
……ああ、自分はいつからこんなに欲深くなってしまったんだろう?
最初はただ見上げていられれば良かったなんて、今ではもう信じられない。
想いが芽吹くのを止められない。
あたしはそんな自分を泣きたくなるくらい『幸せだ』と思っている。
初めは誰よりも綺麗に跳ぶ姿に憧れた。
そして今は、どんな高い困難でも逃げずに立ち向かう勇気に惹かれている。
佐野泉に恋をしている。
そう、強く感じている。
あたしが四つ葉のクローバーから唇を離したとき、不意に背後から声がした。
「……まだ寝ないのか?」
「さ、佐野!?」
予想外の声に思わず椅子から落ちそうになる。
慌てて後ろを振り返ると、佐野はカーテンを開けてはいないようだった。
(今までのこと、見られてなかった……)
あたしはほっとしたような残念なような複雑な気分になった。
「……ごめん、起こしちゃった?」
「いや……でももう遅いし、寝たほうがいいぞ」
「うん」
あたしは手紙と、桜の栞と、四つ葉のクローバーを机の引き出しに大事に仕舞うと、2段ベッドの上に登った。
「おやすみ、佐野」
「おやすみ」
ベッド越しの挨拶。
いつも通りの距離。
ほどなくして佐野の寝息が聞こえてきた。
穏やかで心地よい響きを感じていると、あたしも段々とまどろみを誘われてくる。
(また明日。きっと今日よりも大好きだよ)
近くて遠くの佐野に、そう告白して目を閉じた。
蕾をつけないかもしれない。
もしかしたら自ら手折る日が来るのかもしれない。
でも今は、この想いを大事に育てていこう。
いつか花ざかりになりますように。
そう祈って。